- こんなあなたに
- 週次レビューってナニ?という人
- GTDがうまくいかない人
- GTDをあきめようとしている人
- 困りごと
- GTDをはじめたけど止めたくなったよ
- GTDはムリ
- GTDてどうやったら続けられるの?
こんな困りごとにこたえます。
もくじ
- この記事でお伝えすること
- らずもねのGTD歴
- GTD「週次レビュー」が恐い二つの理由
- タスクの実行漏れに対する恐怖
- 意思決定疲れに対する恐怖
- GTDの「週次レビュー」とは
- 怖さに負けず「週次レビュー」を続けるために
- 意思決定疲れのメカニズム
- タスクを「マイクロ目標の作り方」に倣って細分化しよう
- 本日のらずもねフィーリング
この記事でお伝えすること
GTDのワークフローの一つ「週次レビュー」が恐い。その理由を紹介しています。
- 週次レビューとは[引用:はじめてのGTD ストレスフリーの整理術
,265頁]
- 週次レビューとは,簡単に言ってしまえば頭を再び空っぽにし,先の数週間を見据えた態勢をとるための作業だ。
らずもねのGTD歴
はじめてのGTD ストレスフリーの整理術の著者,デビッド・アレン氏によると,GTDの習熟度には「初級」「上級」「最上級」があると言います。
- GTD 3つの習熟度[引用:はじめてのGTD ストレスフリーの整理術
,378頁]
- 初級:ワークフロー管理手法の基本を取り入れる
- 上級:より高いレベルで人生全体を管理するための統括的なシステムを確立する
- 最上級:GTDのスキルによって生まれたゆとりを活かし,視野を広げて創造的な活動に取り組んでいく
らずもねは2018年1月にGTDをスタート。そもそものきっかけは,様々な環境変化が生じ,やることなすこと全てが上手くいかなくなったため。自己嫌悪する時間が増え,どうにかこの最悪状態を乗り越えたい。そんな,らずもねを救ってくれたのがGTD(Get Things Done)です。
やってみるとわかりますが,GTDには即効性があります。
GTDを一歩進める。その瞬間からモヤモヤした雲が晴れていきます。
GTD開始から6ケ月を振り返り「前向きになれた自分」に気づく
そして6カ月継続すると,いつしか前向きになれた自分に気づきます。
GTDのレビューが上手くいかなくなった途端「まるでダメ地獄」
しかし,気を緩めるとGTDが機能しなくなり「まるでダメ地獄」を味わうはめになります。
GTDは「判断・決定する側が決めないことで,具体的な内容が定まらないタスクが存在しはじめた時」に混乱しはじめる
GTDが機能しなくなる原因は「先送り」。さらに掘り下げると「判断・決定する側が決めないことで,具体的な内容が定まらないタスクが存在しはじめた時」に「先送り」され混乱しはじめる,と分析をしていました。
GTD歴2年目の今,習熟度の自己評価は「初級」。たしかに「初級:ワークフロー管理手法の基本を取り入れる」ことはできました。ただ,しばしば「レビューが恐い」と感じます。最近,「レビューが恐い」と感じる理由が分かりました(以下)。
GTD「週次レビュー」が恐い二つの理由
「週次レビュー」が恐い理由は二つあります。
タスクの実行漏れに対する恐怖
一つ目は,週次レビューによってタスクの実行漏れを発見することに対する恐怖。「先送り」してしまったタスクが今日完了させるべきだったものだと,後になって気づく致命傷とか。痛いミス。「またやっちまった」的なヤツ。「先送り」そのものに自己嫌悪するのに,「許されない先送り」だったことに気づくとマジ凹む。
意思決定疲れに対する恐怖
二つ目は,一つ目の恐怖に慄きながら「先送り」してしまったタスクを再整理する意思決定疲れに対する恐怖。「やろうと決めたのに先送りを続けてしまい,気づいたら1週間経った」と精神レベルの低い状態で,タスクを最新の状態に更新する意思決定はホント疲れます。見て見ぬふりをしたくなります。
GTDの「週次レビュー」とは
GTDのワークフローは「把握する」「見極める」「整理する」「更新する」「選択する」のステップからなります。週次レビューは,「更新する」作業のひとつ。頭を再び空っぽにし,先の数週間を見据えた態勢をとることを目的としています。
この1週間に生じた全ての「気になること」を整理する方法は次のとおりです。
- 明確化する
- 雑多な紙のものを集める
- インボックスを空にする
- 頭の中にあるものを出す
- 最新の状態にする
- 「次にとるべき行動リスト」を見直して更新する
- カレンダーのチェック(過去)
- カレンダーのチェック(未来)
- 「連絡待ちリスト」を更新する
- 「プロジェクトリスト」を更新する
- チェックリストを更新する
怖さに負けず「週次レビュー」を続けるために
「週次レビュー」には「タスクの実行漏れに対する恐怖」と「意思決定疲れに対する恐怖」がつきものです。ただ,怖いという理由から「週次レビュー」を止めてしまってはGTDのワークフローが回転しません。その結果,永遠にストレスフリーに達することができなくなってしまいます。
現在のところ「タスクの一行漏れに対する恐怖」には,慎重にチェックすることぐらいしか思い浮かびませんが,「意思決定疲れに対する恐怖」には光明が見えています。そのヒントが「世界のトップエリートが絶対に妥協しない 小さな習慣」にあります。
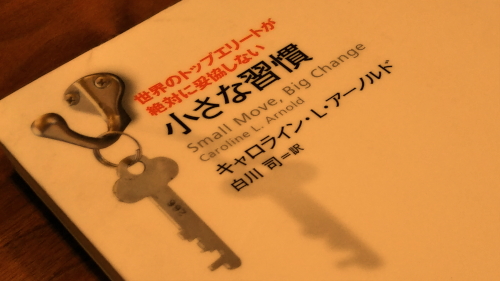
意思決定疲れのメカニズム
意思決定疲れのメカニズムは概ね次のとおりだと言います[引用:世界のトップエリートが絶対に妥協しない 小さな習慣,50~51頁]。
その日の天気や気分,やる気,着替えの用意,飽きの度合い,忙しさなどが障害になると,週5日歩くという誓いを守らない口実になります。
目標をどれくらいこなすかをめぐって自分とかけひきを始め,毎日,目標が流動的になります。
「そもそも週5日がやりすぎだった」「週3日でもいいかもしれない」「今日は歩けなかったから,明日に回してもいいだろう」「強も明日も歩けないから,明後日に回してもいいだろう」。こんな感じで先延ばしが続けば,週末には1日も歩かなかったことで自己嫌悪に陥ることになります。
すばらしい目標を立てたにもかかわらず,だんだん効きめがなくなって最後には挫折するというのを繰り返すのは,こういった心理的なかけひきをするせいです。
今日ではなく明日,今週ではなく来週(今日ハンバーガーを食べられるなら,喜んで火曜日に代金を払うことにする)といったように,いつもかけひきしていると心理的な負担が増えてしまいます。
結局,たまった負担をこなしながら目標を守りつづけることなど絶望的になります。
目標を少しずつ下方修正することで,最後には自分に対する信頼がなくなって,やがて元のルーティンに戻ります。
実行の先送りの影響は,やる気がそがれることにとどまりません。
先送りや目標調整も「意思決定」の一種ですが,意思決定は精神的な活動としてはかなり負担が大きいものだとわかります。
タスクを「マイクロ目標の作り方」に倣って細分化しよう
世界のトップエリートが絶対に妥協しない 小さな習慣は,「マイクロ目標」の作り方を教えてくれます。「マイクロ目標」を作ることは,同時に意思決定疲れを回避することにもなるんです(同著が扱うのは”タスク”ではなく,小さな習慣を継続するための”目標”の作り方です)。
GTDでは,何らかの「目標」を定期的にリマインドすることもあるでしょう。そういった「目標をリマインドする」ことを「タスク」として,「把握する」「見極める」「整理する」「更新する」「選択する」ことがGTDの基本であり,扱うのは「目標」ではなく「タスク」です。
GTDで扱う一つひとつタスクを「マイクロ目標の作り方」に倣って細分化することが,「先送り」と「意思決定疲れ」を減らすことにつながります。
- マイククロ目標
- ルール1:マイクロ目標は簡単にこなせる
- ルール2:何をするかが具体的で,達成できたかどうかがすぐにわかる
- ルール3:マイクロ目標はすぐに効果が現れる
- ルール4:マイクロ目標は人によって違う
- ルール5:マイクロ目標は共鳴する
- ルール6:マイクロ目標はきっかけで動きだす
- ルール7:マイクロ目標を建てるのは一度に2つまで
「粗すぎるダメなタスク」と「細分化された理想的なタスク」
マイクロ目標の作り方は本書に譲りますが,実現したい大きな仕事はタスクに細分化しましょう。
らずもね自身,スマホに登録するタスクが雑だったりします。例えば,登録するタスクが「会議をする」ではダメ。粗すぎるんです。
細分化された理想的なタスクとは,「会議をする」ために「参加者を選ぶ(人数を確定する)」「会議場所を確保する」「参加者にアポをとる」「資料作りのため誰と調整する(会って?,メールで?,電話で?)」「資料作りのため材料A(BとかCとか・・・)を入手する」「議事録を誰かに任せる」といったものになります。
世界のトップエリートが絶対に妥協しない 小さな習慣では,「(目標は)言い訳できないぐらいかんたんに」と教えてくれます。タスクを作る際にも「言い訳できないぐらいかんたん」なことに分解することが大切ですね。
本日のらずもねフィーリング
- 即効性のあるGTDに取組めば,その瞬間から前向きになれます
- 難しいのは「継続していくこと」だと思います
- その理由として,週次レビューの怖さを取り上げました
- マイクロ目標の作り方に倣って,大きな仕事を「言い訳できないくらいかんたん」なタスクに分解することが成功への近道になると思います
